講師紹介と講座内容
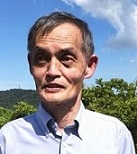
講座名:考古学からの探求 豊臣から徳川へ-城石垣の技術革新と石材調達の変化を考える-
講師名:森岡秀人(もりおか ひでと)(公益財団法人 古代学協会客員研究員)
※新規講座
◆講師自己紹介 1952年神戸市生まれ。現地・現物主義で遺跡・遺物の観察眼を研ぎ澄まし、日本考古学を50年以上専攻。中学校・高等学校と歴史クラブ活動に専念、関西大学文学部史学科考古学研究室時代には、末永雅雄・横田健一・網干善教・薗田香融の諸先生に師事。学生時代には、高松塚古墳、島の庄遺跡、川原寺裏山遺跡、尼塚古墳群、外山谷1号墳、吉志部古墳、千里古窯跡群、乳の岡古墳、定の山古墳、加茂遺跡、中曽司遺跡、垂水遺跡、会下山遺跡、朝日ヶ丘遺跡、八十塚古墳群、城山古墳群、具足塚古墳、金津山古墳、打出小槌古墳などを発掘しました。
芦屋市教育委員会・芦屋市立美術博物館〔兼務〕で文化財保護、遺跡調査、展示学芸、社会教育の仕事に43年間従事。2017年、65歳完全退職。古代学研究会代表、古墳出現期土器研究会会長、(公財)古代学協会客員研究員、考古学研究会全国委員、国立歴史民俗博物館共同研究員、辰馬考古資料館資料調査委員、赤穂市・彦根市・守山市・淡路市・南あわじ市委員。奈良県立橿原考古学研究所共同研究員、大手前大学史学研究所共同研究員など。70歳までに大阪大学・関西大学・神戸大学・滋賀県立大学・立命館大学・梅花女子大学・甲南大学ほかで非常勤講師を務めました。
研究や関心を示すテーマは広く、陵墓古墳、縄文・弥生時代の移行期研究、弥生土器・弥生集落・水田跡の研究、青銅器の研究、古墳出現期の研究、古式土師器の研究、群集墳や地方寺院の研究、考古学と日本古代史との関わり、中世・近世の石切場・石垣の全国的研究も行っています。
共著書や論文は多数あり、『日本史講座』1(東京大学出版会)、『稲作伝来』(岩波書店)、『列島の考古学』弥生時代(河出書房新社)、『講座日本考古学』弥生時代(青木書店)、『弥生土器の様式と編年』近畿編Ⅰ・Ⅱ(木耳社)、『古式土師器の年代学』(大阪府文化財センター)、『初期農耕活動と近畿の弥生社会』(雄山閣)、『季刊考古学』127号・157号編集等。『兵庫県の古代遺跡』(神戸新聞総合出版センター)、『纏向学からの発信』(大和書房)。
趣味は囲碁、雲の観察、里山歩き、美術鑑賞、読書、旅行、石造物巡りほか。
◆講座の内容紹介・受講される皆様へ この50年、城郭の発掘調査が著しく進展し、30年前からは石垣築造には欠かせない石切場の発掘調査や分布調査が増加しています。今回の講座では、考古学研究の手法により、豊臣期から徳川期の天下人の城を見直します。消費の場である石垣、生産の場である石切場の双方の発掘調査や観察調査がドッキングすることにより、新たな研究の視野が開けてきます。刻印の見方や解釈、矢穴技法による石材調達の真価を学ぶことによって、今から400年前の技術力の持続と断絶の歴史像を考えます。合わせて、新たなる「豊徳」期提唱の意義を検討したいと思います。現地講座での学びは、考古学の醍醐味です。健脚向きではなく、初心者向きです。また最後の1回は、昨年1年間の考古学を中心とした発掘成果や研究成果を振り返ります。
◆講座スケジュール
5回講座 水曜日 13:00~14:30 ※8月は休講月です。
第1回 4月24日(水)
内容:織豊期に対しての「豊徳」期提唱、城造りの進化の考古学
第2回 5月22日(水)
内容:大坂城現地講座 石垣刻印・矢穴技法研究・割普請の見どころ・聞きどころ
(JR森ノ宮駅 集合 )
第3回 6月26日(水)
内容:天下人の城、指月伏見城と伏見山伏見城 発掘と踏査
第4回 7月24日(水)
内容: 豊臣大坂城と徳川大坂城、石切場調査の進展
第5回 9月25日(水)
内容:総覧 2023年の考古学界、古代史界
